お問い合わせフォーム
希望日程を選んで必要事項をご記入の上ご送信ください。
24時間中に返信いたします。
\ 3分かんたん送信 !/
.png)
ここ1週間でかなりオンライン授業の経験値が上がってきました。以前勤めていたところでも「遠隔授業」という似たようなものをやったことがあるので実施自体は難しいものではありません。
ただやればやるほど不安になってくるのがオンライン授業です。特に休校がいつまで続くかわからないことも相まって、悩みながら毎日を過ごしています。
オンライン授業も録画配信系の映像教材も「映像である」という点ではまったく同じものです。
オフラインのリアル授業を売りにしていた学習塾にとってはこれはすごく痛いところだと思います。近年の録画配信系の映像教材の進化は目覚ましく、廉価で質の高いものもたくさん存在します。今回の休校措置、そしてオンライン授業への移行で図らずも同じ土俵に立たされることになりました。
同じ土俵で勝負してはいけない気がしています。つまり「自宅にいながら受けられる」という特性だけで勝負しようとしてもダメだということです。
それは映像教材の多様性と質の高さに起因します。僕のオンライン授業より、映像で見せることに特化したプロが作ってて何度も撮り直しができて、わかりづらい、人気のない動画を差し替えることができる映像教材の方が良いような気がします。しかも安い。
「自宅で受けられる」という点だけで選ぶなら断然「映像授業」に軍配が上がります。オンライン教材と映像教材の違いを踏まえた上で戦略的に授業を作っていく必要があります。
ではオンライン教材の特性って何でしょうか。思いつく限り羅列していきます。
結論から言うと、オンライン授業はあくまでもリアル授業の延長線上にあるものです。
新型コロナウイルスの感染予防のための休校措置によってオンライン授業へ移行する塾が増えています。僕がいま勤めている塾も同様です。その場合、すでに在籍している塾生がオンライン授業を受けることになります。
それは、オフラインでの関係性が前提とされた授業と言えます。あくまでもリアルな場を介しての関係があってこそ成立している授業なのです。
オンライン授業はあくまでもリアル授業の延長線上に位置づけられます。その意味でいえば在籍の生徒にとってはつながりのない映像教材にも勝るツールと言えます。
オンライン授業は基本的にその時その場での生配信です。
もちろん授業を録画して配信するという手もありますが、それはもう映像授業と言えるものです。時間の制約があるといて点でもリアル授業の延長線上に位置づけられるものです。
オフラインでの関係性があってリアルタイムという点で生徒とのやり取りも生まれてきます。ここは次に譲ります。
多くの人がオンライン授業に使用しているZoomには「チャット」と呼ばれる機能が付いています。そこで質問や解答をしてもらうというやり取りが可能になっています。またLINE等のツールで質問を受け付けたり、課題を提出したり、欠席者への連絡をとったりすることもあります。
問いかけても返事をしてくれない映像教材と違って、応答性を備えたコミュニケーションの可能性がオンライン授業にはあります。
オンライン授業はリアルタイムで行われるという時間的制約があります。また出席が管理できるという側面があります。
オンライン授業には弱い拘束性があるのです。(リアル授業に比べれば弱いものですが…)
これは映像教材にはないものです。映像教材の挫折は「見ない」「続けられない」ことでしょう。縛ってくれる何かがなければ勉強に向き合えない生徒が一定数いるのも確かなことです。そのため映像教材系の塾では「学習管理」が大きなテーマとなっています。
オンライン授業には勉強に向き合わせるための拘束性という武器が備わっているのです。
ここまでのことを整理してみると、オフラインの関係性を前提としたリアルタイムな授業進行で、生徒とのコミュニケーションの機能を残しつつ自宅で受けられるのがオンライン授業だと言えます。
映像教材にない、オンライン授業の特性を活かさなければ太刀打ちできないのではないでしょうか。
映像教材の利便性は目を見張るものがあります。廉価で高品質、時間も場所も問わず勉強することができます。Zoomを使った(しかも時々通信のダウンが起きる)オンライン授業は特性をフルに活かさなければ勝つことは難しい。これが今の僕の正直な感想です。
僕がこんなにオンライン授業に不安を感じているのは、「いつまで休校が続くのか?」という懸念を持っているからです。
いつまでなんでしょう?1カ月、2か月ならまだオフラインでの関係性を前提に内部生だけに授業を配信すれば良いかもしれません。
でも半年、1年だったらどうでしょう?オンライン授業だけで生徒を伸ばせるでしょうか。オンライン授業だけで生徒を集め、生きていく事はできるでしょうか。そういうことを考えながら今の状況をやりくりしていく必要があります。
休校が半年以上続いた場合のケースを想定すると、以下の状況をクリアしなければなりません。
半年もすれば多少の問い合わせも来るでしょう。新規入会者も入ってきます(たぶん)
でもその生徒はオフラインでの関係性を持ちません。
リアルな教室という場で同じ時間を共有したことのない生徒相手にオンライン授業をすることになります。これは結構大変なことではないでしょうか。映像教材と全く同じ位置づけで受講することすらあり得ます。
オンラインで授業を配信するだけではいけません。特性(特にコミュニケーション)を活かさなければ生徒は授業にコミットできなくなり。成績を上げることが難しくなることが予想されます。
映像教材の弱点として拘束性がないこと。オンライン授業の特性として弱い拘束性を持つことはさっき書きました。この弱拘束性は休校が長期化した時に弱点となりえます。
リアル授業の拘束性は威力を持ってて、生徒を勉強に向き合わせることが可能です。でもオンライン授業はそれが弱い。勉強に向き合えない生徒が増えてしまう。授業の離脱が増え、欠席率が高くなる。 そうなると学習効果が低くなるのは明らかです。
悲観的予測に過ぎませんが、同じように感じているオンライン授業者も多いはずです。映像教材に比べるとまだ良いような気がするものの、弱みとは言えるでしょう。どうにかクリアしなければならない点です。
長期化する場合に備えてこれらの点を見越した指導を実践していかなければならないなと感じています。
今日はオンライン授業をやっていて、休校が長期化した場合のネガティブな側面を書き出してみました。これらをクリアしなければ小さなオンライン指導塾は生きていけない気がしています。そしてそれは開校予定のベンガルも同じこと。焦りは相当なものです…。
この事態が収まって塾の授業が再開できれば良いんですけども…
2021年にもオンライン授業を実施!小学生クラスも使いこなしています!
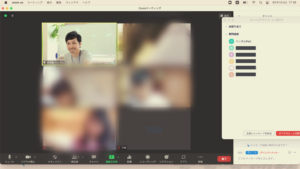
-300x158.png)
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!